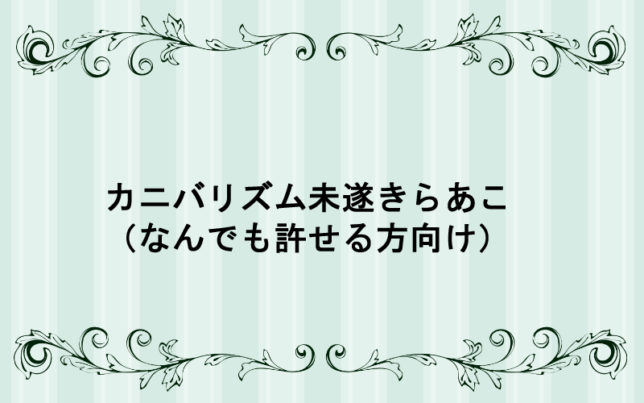「さすがのエルザさまも、にんげんのおにくは、たべたことないよねえ」
ちいさな手が、ためらいなく伸びてくる。膝に触れ、それから太腿をじれったいくらいの遅さで撫でる。その手は細くともやわらかで、「女の子」という言葉が頭をよぎる。
「なんのつもりですの、花園きらら」
「なんのつもりって?」
「なんでこんなことをしているのかって訊いているんですのよ」
四つ星学園S4寮、早乙女あこの自室。ヴィーナスアークの出航に間に合わなかった花園きららを泊めることになって、部屋へ招き入れて。ただそれだけだったのに、どうしてこんな状態になっているのだろうと、あこは頭を回転させる。けれど、思い当たることはなにもない。あこは壁に背中を貼りつけるようにして、ベッドの上に座っている。正面からはきららがスプリングをきしませながらにじりよってきていて、これ以上逃げられるスペースはない。
ついさっきまで、ベッドに腰かけて他愛のない話をしているだけだった。主にきららが喋って、あこは気のない返事をして。それが、急に。まるで、ひとが変わったみたいに。
「にんげんのおにくって、どんなあじがするのかなあ。あこちゃんしってる?」
「知りませんわよ、そんなこと」
「あまいのかなあ、しょっぱいのかなあ。おいしいのかなあ」
舌なめずりするきららの口元から、一滴、顎を伝ってシーツの上にぱたりと落ちた。それを見て、あこは背筋に寒気を覚える。心なしか、きららの息遣いが荒く、まるで飢えた獣のよう。きららはさらにあことの距離を詰めながら、手の甲で扇情的に口元をぬぐった。
「きららねえ、あこちゃんのこと、まえからおいそしうだなあっておもってたんだよ」
可愛らしく小首をかしげてみせたきららの瞳には、何の色も浮かんでいない。
――こわい。
はじめて、そう思った。
花園きららのことを。
「きらら、あこちゃんのこと、たべたいなあ」
「ちょっと、きらら……!」
小柄な身体に似合わず、きららは以外にも力が強い。抵抗しようとするあこの手首を掴むと、壁に押し付けて、さらにその上から力を加えてくる。手首に、痛々しい痕跡がついてしまうのではないかと思うくらいに。あこは、顔をしかめて身じろぎをする。そうしながら、精一杯の虚勢をはって、言う。
「あなた、さみしいだけですわよね」
きららは、応えない。
「エルザ・フォルテに置いていかれたことが、さみしいんですわよね」
「そうだよ」
スカートがまくれあがって、そこに、きららの吐息がかかる。きららの表情は、あこからは見えなくなって、この場にそぐわないような、ふんわりと結われたパステルカラーの髪が視界に無理矢理入ってくる。
生あたたかい、生々しい。
「きらら、とってもさみしくて、とってもくやしいんだよ。だからあこちゃん、きららのこと、なぐさめてよ。さみしいときはね、おなかがすいているときなんだって。エルザさまは、おなかがすいたときには、おにくをたべるんだよ。きららも、エルザさまといっしょにいるようになってから、おにく、だいすきになったんだあ。だからあこちゃんのおにく、たべさせて。きららもう、さみしくて、さみしくて、おなかぺこぺこなんだよ」
太腿に、嚙みついた。
それは戯れのような生やさしいものではなくて、本当に噛み千切ろうとしているような、そんな歯の立て方だった。一滴の甘さも陶酔も伴わない痛みが、全身に走る。たべられてしまう、と思った。そう思わせる気配を、きららは全身から、発していた。
「いい加減になさい……花園きららっ!」
力を振り絞って頭を押しのけたら、意外にもあっけなく、きららはあこから口を離した。きららの口からは唾液が糸を引いていて、名残を思わせる。あこは反射的に目をそらした。
きららは唇をぺろりと舐めて、それからベッドに倒れこむように仰向けに寝転んだ。
「あーあ、ざんねん。あこちゃんのおにく、たべてみたかったなあ。あこちゃんのふともも、やわらかいのにかみきれないなんて、ふっしぎぃ」
噛み千切られるのではないかと思わせる痛みを感じたものの、あこの内腿には歯型が残っているくらいで、出血すらしていなかった。思っているよりも、自分の身体は丈夫にできているのか。それとも。
「ねえ、あこちゃん。あこちゃんがさみしくなったら、きららのこと、たべていいからね」
「しませんわよ、そんなこと」
「えー、そうかなあ」
「わたくしはあなたとは違うんですのよ」
「あこちゃんだって、さみしいくせに」
<了>