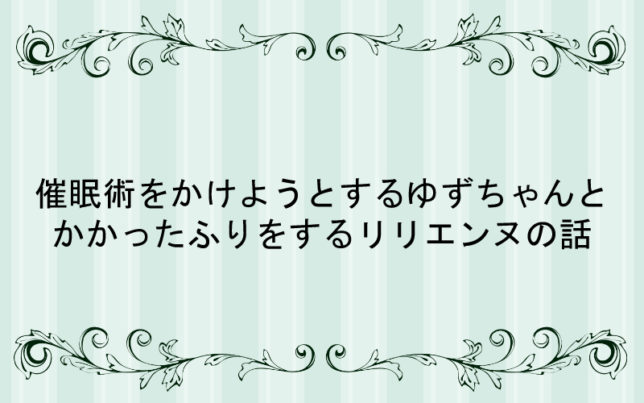「リリエンヌはだんだん眠くなる……眠くなるんだぞ」
「あの、ゆず」
「眠くなる~眠くなるんだぞ~」
なぜこのような状況になったのでしょう、とわたしはゆずに押し倒された状態で、ぼんやりと考えました。
寮の自室のベッドに、仰向けに寝ころんでいるわたし。そこに跨るようにして、わたしの顔を覗き込んでいるゆず。ゆずとわたしの顔の間で、ゆらゆら揺れる五円玉。
「リリエンヌは眠いぞ~すぐに眠ってしまうんだぞ~」
目を細めて、紐をくくりつけた五円玉をゆらゆらさせるゆずを見ていたら、眠るどころか笑ってしまいそうになりました。ゆずのこんなに無表情な顔(を一生懸命装っている顔)は、滅多に見られるものではありません。
ことのはじまりは十分前、ゆずがわたしの部屋を訪ねてきたときにさかのぼります。ゆずは入室するなり「リリエンヌ、ちょっとそこに横になってみてほしいぞ」と、わたしに言いました。思えば、このときゆずは右手を後ろに隠すようなポーズをとっていたような気がします。そしてわたしがベッドに横になるや否や、ゆずによる催眠術が開始されたのです。
「リリエンヌは眠くて仕方ないんだぞ~いまにも眠ってしまいそうなんだぞ~」
そういえば、昨晩ゆめさんやローラさんが出演した番組で、催眠術の特集がなされていたことを思い出しました。ゆずはおそらくそれを見たのでしょう。ゆずは自由奔放に見えますが、生徒会長として、ほかの生徒たちのことをきちんと見守っているのです。四ッ星学園の生徒が出演した番組やステージは、録画をしてでも、忙しい仕事の合間にチェックしていることを、わたしは知っています。
「眠ってしまうんだぞ~リリエンヌは実はもう眠っているんだぞ~」
「すうすう」
「えっ?」
「すやすや」
「んん?」
わたしは目を閉じ、「すうすう」「すやすや」と、寝息の擬音を呟きます。催眠術ごっこという、幼いころにしたような遊びをするのも、たまには楽しいかもしれません。
ゆずは寝たふりをしたわたしの頬を、ぺたぺたと優しくなでるようにたたきました。
「リリエンヌ? おーい、リリエンヌ……はっ! もしかして催眠術成功? やったー、やっとリリエンヌに催眠がかかったぞ! わーい! ……って、こんなに大声でしゃべってたら、リリエンヌ起きちゃうよね。いけない、いけない」
そっと薄目を開けて窺ってみると、ゆずがあまりにも真剣な顔をしていたので、わたしはあわてて再び目を閉じました。
――ゆずは、遊びではなく本気で催眠術をかけようとしていたのでしょうか?
――何のために?
それはわからなくとも、ゆずが真剣に催眠術をかけようとしていたのなら、わたしがこうして催眠にかかったふりをしているのは良くないでしょう。
わたしは目を開け、身体を起そうとしました。けれど、結局そのようにはなりませんでした。
そうしようとしたとき、ふんわりとした猫っ毛のくすぐったさを頬に感じたからです。
「リリエンヌは、大丈夫だぞ」
すぐ耳元で、ささやかれた声。
優しくてやわらかい、ゆずの声です。
「リリエンヌは大丈夫だぞ……リリエンヌは毎日苦手なトレーニングを頑張って、すこしずつ体力もついてきたから、大丈夫だぞ。だから、今年の夏は休学しなくても、リリエンヌは、大丈夫だからね。夏も思いっきり、アイカツ、できるからね」
――ゆずは、知っていたのですね。
わたしが、身体が弱いために夏はこの学園でアイカツができなくなってしまうことを、寂しく思っていたことを。「個性は様々なのだから、レッスンやアイカツの仕方も様々で良い」と言いながらも、療養している間に遅れをとってしまうことを、その実歯がゆく思っていたことを。
そして、今年は高原で療養するかどうか、迷っていたことも。
「ゆず」
わたしはゆずの首に両腕を回しました。ゆずはわたしの耳元に顔を寄せているため、顔は見えません。もちろん、ゆずからもわたしの顔は見えません。
「ゆず」
「えっ、リリエンヌ!? ゆずまだ催眠解いてないぞ!」
「わたし、今年は高原にはゆきません」
息をのむのがわかりました。
わたしは腕にすこしだけ力を込めて、続けます。
「ここにいます。わたしには、ゆずと一緒にこの学園を守るという役目があるのですから」
「リリエンヌ……!」
どのような表情をしているのかなど、顔を見なくてもわかります。
きっとそれは、ゆずも同じ。
「無理は、しちゃだめだからね」
「ええ、わかっています。ねえ、ゆず。もしもわたしが無理をしてしまいそうになったら、ゆずが止めてくれますか」
「もっちろんだぞ!」
カーテンの隙間から差し込む日差しと、ほんのり汗ばんでいるゆずの身体は、夏の訪れを予感させます。
「寒い季節にしか活動できないからツンドラの歌姫なのだろう」とは、もう言わせません。
太陽がいちばん明るく輝く夏に、わたしは、それ以上に輝いてみせます。
愛するひとと、愛するドレスと共に。
<了>