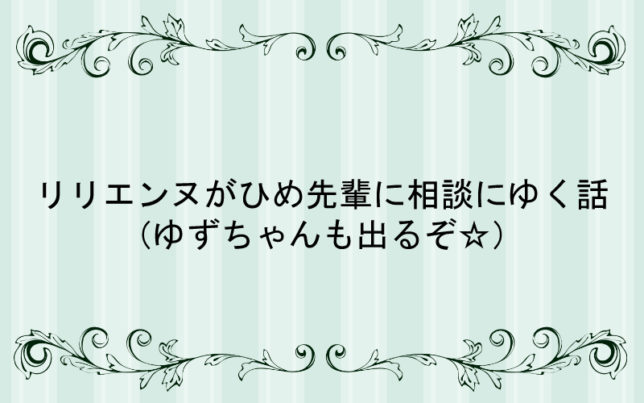新学期を迎えたばかりの、ある休日。わたしは寮の自室で机に向かっていました。
「そろそろ作りはじめる必要がありますね……」
愛用の筆記用具とスケッチブックを取り出し、机に広げます。
わたしは6月のゆずの誕生日に、自作のお洋服を贈ろうと考えていました。以前わたしがブランドを立ち上げた際、ゆずは自分にも作ってほしいと言ってくれたのです。ですがブランドを立ち上げてからというもの、店頭に並べるお洋服の制作やS4戦の準備などで忙しく、未だゆずのためのお洋服を作ることができずにいました。そこで今年の誕生日には、ぜひともわたしが作ったお洋服を着てもらいたいのです。
そこで問題がふたつ。
ひとつは、ゆずの誕生日が初夏であるということ。わたしは梅雨の時季から夏の終わりにかけて体調を崩してしまうため、おそらく誕生日直前は作業があまりできないでしょう。まだ春とはいえ、いまのうちに進めておかなければ、最悪間に合わなくなってしまうかもしれません。
それになにより、ほかでもないゆずのために作るお洋服なのですから、たっぷりと時間をかけたいという思いもあるのです。
ふたつめは――。
「これも……違います」
わたしは自分自身のブランド・ゴシックヴィクトリアのカタログをめくりながら、ため息をつきました。
ふたつめの問題。それは、デザインがなかなか決まらないことです。
ゆずは可愛らしい上にダンスで引き締まった美しい身体をしています。ですから基本的には、何を着ても似合うはずなのです。ですがやはり、ゆずの魅力を最大限に引き出すことができるお洋服をデザインしたい。ゆずが身に着けることで、はじめて完成するような、そんな一着を。
「ゴシックヴィクトリアのお洋服を身に着けたゆずも、見てみたいですが……」
普段ポップなドレスやお洋服を着ることが多いゆずが、フリルとレースで飾られたワンピースを身にまとっているところを想像して、つい口元がゆるみます。
ですが、ゆずの魅力を引き出せるかというと――。
わたしはカタログを閉じて、立ち上がりました。初代ドイツ帝国宰相・ビスマルクは言いました。「愚者は自分の経験に学ぶと言う。私はむしろ他人の経験に学ぶのを好む」と。
机に向かって頭を抱えていても、なにもはじまりません。わたしは「彼女」の経験に学ぶべく、寮の自室を後にしました。
***
そのお部屋は、主のように上品で優雅な紅茶の香りでいっぱいでした。
「どうぞ、リリィちゃん」
「ありがとうございます、ひめ先輩」
わたしは四ッ星学園高等部の寮の一室を訪れていました。S4に与えられる専用の寮のお部屋と比べると――実際に入ったことがあるのは舞組用の部屋だけですが――少々手狭ながら、ひめ先輩らしい可憐さに満ちたお部屋に仕上がっており、とても素敵です。
「お誕生日にお洋服を贈るなんて、とっても素敵ね」
ひめ先輩は紅茶を片手に、ふんわりと微笑みました。
わたしは紅茶のカップから手を離して、目の前のひめ先輩に尋ねます。
「ひめ先輩。先輩は、お洋服作りで悩んだことはありますか」
「あるわよ、もちろん」
ひめ先輩はマイリトルハートというブランドを、S4になった際に自ら立ち上げました。四ッ星学園の生徒が「自分のブランド」を持つ場合、通常はどこかのブランドと提携し、ミューズとしてそのブランドに関わってゆくことになります。ですから、ひめ先輩やわたしのような例は、ほかにほとんど見当たりません。
「わたしは、わからなくなってしまったみたいなのです。大切なひとに、いちばん似合うお洋服を作りたいのに、わたしではそれができないような気がしてしまって」
「それはどうして?」
「ゴシックヴィクトリアのお洋服では、そのひとを最も輝かせることは、きっとできません」
ひめ先輩はすこしの間、思案顔で黙っていました。それからおもむろに立ち上がって、本棚から一冊のアルバムを取り出したのです。
「これを見て、リリィちゃん」
開かれたページに写っていたのは、ひめ先輩、そして、もうひとり。
写真の中のひめ先輩は、一目でマイリトルハートのものとわかる、リボンやフリルが品良くあしらわれたパステルカラーのお洋服を着ていました。そして、もうひとりの方は。
「このお洋服ね、どちらもわたしがデザインしたものなの」
「これを、ひめ先輩が?」
わたしは信じられない思いで、アルバムを見つめました。ひめ先輩の隣に写っているひとが身に着けているのは、マイリトルハートのラインナップにはないような、スポーティなデザインのものだったのです。
「……ですが、袖口にさりげなくちいさなリボンが飾られています。トップスはシンプルながら、裾のシルエットが可愛らしい」
一見すると、そのお洋服はシンプルかつスポーティな雰囲気のもので、ひめ先輩のデザインらしくないように思えます。ですが、よくよく観察してみると、細部にしっかりと、ひめ先輩の個性が現れていたのです。前面に押し出されることなく、あくまでさりげなく。このお洋服は、紛うことなき、ひめ先輩がデザインしたものであるとわかります。
「確かに、ブランドのイメージは大切よ。ゴシックヴィクトリアのお洋服を求めてお店に来てくださるひとたちは、ゴシックヴィクトリアらしいものを期待している。わたしのブランド・マイリトルハートもそう。だからステージドレスやお店に並べるお洋服は、ブランドのイメージを大切にしたものでなくてはならないと思っているわ。でもね、リリィちゃん」
アルバムから顔を上げると、ひめ先輩と目が合いました。
「たったひとりに着てもらうためだけに作るお洋服は、その限りではないと思うの。ゴシックヴィクトリアのデザイナーとしてではなく、白銀リリィというひとりの女の子として、お洋服をデザインしてみたら良いんじゃないかしら」
「ひとりの女の子として……」
ひめ先輩のその言葉は、わたしが自分で自分を閉じ込めていた、鳥かごの鍵を開けてくれました。
思い出したのです。まだブランドを持つ前、のびのびと自由にデザインをしていたころのことを。あのころは、ひとつのイメージやテイストにとらわれることなく、自分が本当にわくわくするもの、心ときめくものを、作ることができていました。
いつのまに、わたしはその自由な心を忘れてしまっていたのでしょう。
ブランドを大切にするあまり、知らないうちに自分で自分のイメージにとらわれ、がんじがらめにされてしまっていたのです。
「ひめ先輩。わたし、やってみます。わたしが最も大切に想っているひとに似合うお洋服を、ただの白銀リリィとして作ってみます。否――作りたいのです」
「ええ、頑張って。リリィちゃんならきっとできるわ」
わたしの中に、急にアイディアがあふれだしてきました。デザイナーではない、ただのわたしとして自由にデザインをする。そう思うだけで、ゆずに着てほしいと思うお洋服の、テーマや色や装飾やシルエットが、次々に思い浮かんで止まりません。
「申し訳ありません、ひめ先輩。紙と、それからなにか描くものをお借りできませんか」
「もちろん」
ひめ先輩が立ち上がったそのとき、お部屋のドアが勢いよく開かれました。
「リリエンヌー!」
大声の主は、もちろんゆずです。
「やっぱりここだったぞ!」
ゆずはピースサインを掲げて、太陽のような満足気な笑顔を浮かべていました。
「ゆず! どうしてここにいるとわかったのですか?」
「えっへん! リリエンヌのことなら、ゆずはなんでもお見通しなんだぞ!」
「あらあら。さすがね、ゆず。リリィちゃんもすぐにゆずの居場所を見つけられるみたいだし、ふたりは本当に仲良しなのね」
「あーっ、ふたりでケーキ食べてる! ずるいぞ! ゆずもゆずもー!」
「はいはい、ゆずにも紅茶淹れるわね」
ひめ先輩はゆずの分の紅茶を用意しにゆく際、わたしの肩に手を置いて、耳元でささやきました。
「――プレミアムレアドレスも、楽しみにしているわね」
ひめ先輩はにっこりと微笑むと、小声で続けます。
「リリィちゃんは、S4にならなければプレミアムレアドレスを作ることができないって考えていたのよね。確かに四ッ星ではそういう風潮があるけれど、それはアイドル界全体の決まりではないわ」
「ひめ先輩……」
ひめ先輩はバレリーナのような優雅な動作で、さっとわたしから離れると、いつの間にかお部屋に入って室内を楽し気に眺めていたゆずにも聞こえるように、言いました。
「わたしたちアイドルが型にはまりすぎていたら、見てくださるファンの方たちも、おもしろくないじゃない? まずはわたしたちが、自由に楽しみましょう」
「そうそう、自由がいちばん! 楽しいのがいっちばーん!」
自由という言葉に反応したゆずが、ぴょんと飛び跳ねながら言います。
「ゆずは自由すぎます」
「ミキも心配していたわよ」
「えーっ、そんなあ、ふたりともー!」
自由すぎるアイドル。ゆずは時に、そんな風に呼ばれることがあります。自分自身にすらとらわれず、自由に大空を舞う鳥のようなゆず。そんなゆずに似合うお洋服を、ゆずがゆずらしく、自由でいられるお洋服を、わたしはデザインしたいと思います。
――そしていつか、プレミアムレアドレスも。
自由な心で、自由なわたしで。
籠の中の小鳥はもう、飛び立つ準備を終えたのですから。
<了>